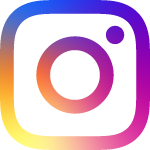小学校のプログラミング教育ってどうなってるの?5年目のリアルをチェック!
2020年、日本の小学校でプログラミング教育が正式に必修化されました。 それから5年、実際にはどのように教えられているのでしょうか? 実際のデータや先生の声をもとに、リアルな現状をお伝えします。
プログラミング教育の「目的」は?
小学校におけるプログラミング教育の目的は、「プログラミング的思考」を育てることです。 つまり、「論理的に考える力」や「順序立てて問題を解決する力」を伸ばすことがゴールです。 その目的を達成するために、文部科学省が設定したプログラミング教育の時間数の目安は、たった年間およそ6時間! 週に1回どころか、2か月に1回1時間やる程度です。 そしてその貴重な6時間でさえ、しっかりと先生たちが教えられているとは言えない現状があります。 なぜでしょうか?
1. 教員のスキル不足
実は、文部科学省が2022年に行った調査では、 小学校教員の約70%が「プログラミングを教えることに自信がない」と回答しています。 理由は簡単で、現在現場にいる先生方の多くは、学生時代にプログラミング教育を受けていない世代だからです。 たとえば、ある県では、 「パソコンの電源を入れるところから説明が必要だった」 という例も報告されています。
2. プログラミング教育の「形だけ」問題
2023年に実施されたある調査では、 小学校教員の約60%が「プログラミング教育を算数や理科の授業に“関連づけて”実施している」と回答しています。 しかしその中身を見ると、 実際は 「やったこと」にして授業が終わる といったケースも多いことがわかっています。 もちろん、学校や地域によって状況は異なるため、住んでいる地域によってかなり差があるのが現状です。
たとえば、あまり力を入れていない学校では、Scratchで猫を動かすだけで終わってしまうこともあります。 一方で、教員研修がしっかりしていたり、地域や教育委員会の支援がある地域では、実践的な授業がしっかり行われているケースが多く見られます。 どの事例にも共通しているのは、「教える人の準備」と「学校全体での協力」があってこそ、うまくいっているという点です。
まとめ
小学校のプログラミング教育は、必修化5年目にして、まだ「発展途上」というのが正直なところ…教員のスキル不足、地域格差、「形だけ」の授業など、現場には多くの課題が残っています。 さらに、2025年から大学入試にもプログラミングが取り入れられています。 もし学校側がまだ十分に対応できていない場合は、自宅学習やプログラミング教室の活用といった対策を考える必要もありそうですね。