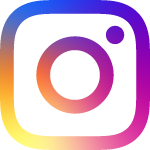高校のプログラミング授業は?意外とバラバラなその実態
前回まで、小学校と中学校のプログラミング授業についてご紹介してきました!
小学校や中学校でのプログラミング教育が進む中、「高校ではどんなことを学ぶの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、高校でのプログラミング授業の実態について見ていこうと思います(*’▽’)
教科書も言語も学校によってバラバラなプログラミング教育
高校では、2022年度から「情報Ⅰ」が必修化、2025度には「情報Ⅰ」が大学入試科目に追加され、すべての生徒がプログラミングを学ぶ時代になりました。
しかし、高校で使用される教科書や教材は学校によって異なるため、扱う言語や内容にもバラつきがあります。
主に使用されているのは、Python、JavaScript、C言語、HTML/CSSなど。その中でもPythonを使う教科書が56.7%と、今もっとも主流な言語となっています。
授業は年間平均約70回(58時間程度)行われ、基礎的なアルゴリズムやプログラムの構造を学ぶ学校が多いです。たとえば、都立雪谷高校ではPythonでの学習後、micro:bitやプログラミングカーを使って、実際にプログラムを動かす実践授業を行っています。一方で、Scratchを使ってゲーム作りに取り組む高校もあり、教科ごとの方針はさまざまです。
また、注意したいのが「教える側」の課題です。現在、情報科教員の不足が深刻で、臨時免許や他教科の先生が担当しているケースも多いのが実情です。そのため、授業の質や専門性には学校間で差が出ているという声も。さらに、大学入試で出題される擬似言語DNCLは通常の授業では使われず、共通テスト対策でのみ登場します。
まとめ
高校でのプログラミングは、受験科目となったことで重要性を増し、基礎から実践へと一歩進んだ内容が求められますが、前提となる知識の有無で理解度に大きな差が出てしまうこともあります。
当教室では、小学生のうちからPythonやWeb言語に楽しく触れられるカリキュラムをご用意しています。
高校で困らないために、今から楽しみながら学ぶ。そんな一歩を、ぜひお子さまと一緒に踏み出してみませんか?